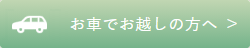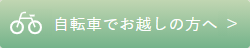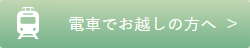《“噛む力”の物語 第2回》~歯が生え変わる時期に起こること ~ 学童期の歯と顎の発達

1.歯が生え変わる時期に起こること
6歳前後になると、最初の永久歯「6歳臼歯(第一大臼歯)」が顔を出します。
この歯は、すべての噛み合わせの軸になる大切な歯。
でも歯ブラシが届きにくく、いちばん虫歯になりやすい時期でもあります。
生え変わりの時期は、乳歯と永久歯が入り混じる混合歯列期。
歯の高さも並びも揃わず、噛み合わせが一時的に不安定になります。
この時期の食べ方・姿勢・呼吸のしかたが、
のちの歯並びや顎の発達を大きく左右します。
2.噛む力と姿勢の関係
噛む力は、口だけの問題ではありません。
首・肩・背中の筋肉と連動して働いています。
食事中に背中が丸くなったり、頬杖をつくクセがあると、
下あごが後ろに引かれ、噛み合わせがずれやすくなります。
イスの高さを調整して、足の裏が床につくように座るだけで、
体の軸が安定し、噛む動きもスムーズに。
「姿勢がいい子は集中力が高い」といわれるのは、
噛む運動と全身の姿勢が密接に関わっているからです。
3.口呼吸に注意したい理由
口呼吸は、最近とても増えている癖のひとつです。
花粉症やアレルギー、鼻づまりなどがきっかけで、
無意識のうちに口が開いたままになっているお子さんも少なくありません。
口呼吸が続くと、唇が乾きやすくなり、
唇を閉じる力(口輪筋)が弱まって、
舌の位置が下がる傾向があります。
この状態が長く続くと、上の前歯が前方に傾きやすくなることがあります。
ただし、「口呼吸=出っ歯になる」と言い切れるわけではありません。
指しゃぶりが長く続いたり、飲み込むときに舌で前歯を押す癖(舌突出癖)があったり、
もともとの顎の骨格が小さいなど、
いくつかの要因が重なって歯並びに影響していくのです。
だからこそ、どれか1つを責めるよりも、
「今の呼吸や癖を少し見直していこう」というくらいの意識で十分。
お家では、鼻呼吸を促す遊びを取り入れてみましょう。
たとえば、
-
風船を膨らませる
-
ストローで水を吹く
-
ハーモニカを吹く
といった遊びの中で、唇を閉じる力を自然に鍛えられます。
お口が閉じられるようになると、
噛む力・発音・表情筋までバランスよく育っていきます。
歯並びの土台は「呼吸と筋肉のリズム」から作られていくのです。
4.食べ方と顎の発達
学童期は、顎の成長が最も活発な時期。
この時期にしっかり噛むことが、歯が並ぶスペースを作ります。
やわらかい食事が続くと、顎の発達が追いつかず、
歯が重なって生える「叢生(そうせい)」や、
前歯が閉じにくい「開咬(かいこう)」、
受け口(反対咬合)などが起こりやすくなります。
ご飯をしっかり噛む、根菜や少し歯ごたえのある魚・肉を食べるなど、
日常の食事の中で“よく噛む時間”を意識しましょう。
噛むことは顎の発達だけでなく、発音や表情の筋肉にも関係しています。
5.歯並びの変化と矯正のタイミング
「歯が少しガタガタしてきた」「前歯のすき間が気になる」
そんな変化に気づくのが、ちょうどこの時期です。
でも、いきなり矯正歯科に行くのは勇気がいりますよね。
まずはかかりつけの一般歯科で相談するのがおすすめです。
当院でも、日常の定期検診の中で歯並びや噛み合わせを確認し、
必要に応じて矯正専門医をご紹介しています。
永久歯が生えそろうまで待つケースもあれば、
顎の成長を促すために小児期から始める方が良い場合もあります。
タイミングの見極めが大切なので、
気になった段階で一度ご相談ください。
6.当院でのマウスピース矯正と連携治療
クリスタルデンタルクリニックでは、
中高生から成人の方を対象にしたマウスピース矯正を行っています。
透明で目立ちにくく、食事や大切な行事のときは取り外せるため、
学校生活やアルバイト、部活動との両立がしやすいのが特徴です。
一方で、小児期(乳歯と永久歯が混在する時期)には、
顎の骨の成長をコントロールする矯正治療が必要なケースもあります。
この段階での治療は、専門の矯正歯科での対応が最も確実です。
そのため当院では、
1️⃣ 初期診断・相談 → 2️⃣ 信頼できる矯正専門医へのご紹介 → 3️⃣ 矯正後の予防ケアとむし歯治療
という連携体制をとっています。
つまり、「どこに相談すればいいかわからない」という方も、
当院に通っていただければ、成長段階に合わせた最適な治療先をご案内できます。
矯正を終えた後の定期メインテナンスや虫歯予防、
万が一のトラブルへの対応まで、しっかりサポートします。
7.仕上げ磨きの卒業期と、自分で守る力
小学校高学年になると、「もう自分で磨けるよ」と言う子が増えてきます。
確かに、自立の第一歩ではありますが、
実際には奥歯の溝や歯と歯の間の汚れが残りやすいのがこの時期です。
「ちゃんと磨いてる」と本人は思っていても、
歯科で染め出してみると、磨き残しがまだたくさん。
このギャップを埋めるには、
家庭での見守りに加えて、「定期的なTBI(歯磨き指導)」がとても効果的です。
歯科衛生士は、ただ磨き方を教えるだけでなく、
その子の性格や手の動かし方に合わせて、
「できる方法」に変換してくれます。
親が何度言っても聞き流していたのに、
「歯医者さんのお姉さんに言われたから」と素直に直す子、意外と多いんです。
TBIは叱る時間ではなく、「自分の口を知る時間」。
自分の磨きグセを知ることで、
「歯みがきって意外と奥が深い」と気づく子もいます。
親の声より届く第三者の声を、うまく活かしてほしい。
歯科医院を「磨き方の味方」として上手に使うことが、
子どもが自分の口を守る力を育てる近道になります。
8.親が見守る安心と、子どもが育つ自信
学童期は、心も体もぐんと成長し、
見た目はしっかりしていても、歯やお口の中はまだ発展途中です。
だからこそ、親のちょっとした「気づき」がとても大切。
「最近、口臭が強くなった気がする」
「食べたあと、よく奥歯を気にしている」
「冷たいものを食べると顔をしかめる」
「歯ぐきが赤く腫れている」「歯みがきを嫌がるようになった」
こうした小さな変化は、初期むし歯や歯肉炎のサインかもしれません。
見逃さず、早めに受診することで、大きな治療を防ぐことができます。
きちんと定期検診を続けていれば、
いきなり「神経を取る(抜髄)」といった処置が必要になることは、ほとんどありません。
大切なのは、「異変があったときに早く気づいてあげること」。
そしてもうひとつ大事なのが、歯医者さんへの心理的な距離です。
子どもは「怖い」と思うと、
「大丈夫」「何ともない」と無意識に避けようとする傾向があります。
そんなときは、家庭での声かけを少し変えてみましょう。
「歯医者さんのお姉さんにピカピカにしてもらおうか」
「そろそろお口のお掃除に行こうね」
そんな前向きな言葉で、
歯医者を「痛い場所」ではなく「気持ちよくなる場所」として印象づけることができます。
親が気づいて、見守って、そして明るくつないでいく。
その小さな積み重ねが、
将来の歯の健康と、子どもの自信を育てるいちばんの近道です。
💬 そして次回は…
子どもが自分の力で選び、動き始める「思春期」のお話です。
部活や受験、夜更かし、食生活の乱れ……そんな時期だからこそ、
「自分で守る歯の力」が問われていきます。
次回、《“噛む力”の物語 第3回》
~思春期の歯と心──自分で選ぶケアのステージへ~
どうぞお楽しみに。
🦷 川口市でお子さまの歯の相談なら
クリスタルデンタルクリニックでは、
6歳臼歯のシーラント処置をはじめ、
お子さまの虫歯治療や予防ケアにも力を入れています。
痛みの少ない丁寧な治療と、
お子さまが安心して通える優しい診療を心がけています。
定期検診では噛み合わせのチェックや、
歯並びの変化に合わせたアドバイスも行っています。
必要に応じて、信頼できる近隣の矯正専門医をご紹介し、
思春期以降には学校生活や部活動に支障の少ない
マウスピース矯正にも対応しています。
📍 川口駅から徒歩3分/提携駐車場1時間15分補助/駐輪場3時間無料
🔗 詳しくは当院公式ブログをご覧ください
👉 https://crystal-dental.jp/
✨「噛む力」を育てることは、未来の健康を育てること。
私たちはその歩みに寄り添い続けます。